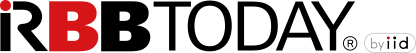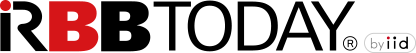【視点】岐阜の伝統工芸「ぎやまん陶」に世界が注目!その秘密とは?
エンタープライズ
その他
-

【デスクツアー】真似したい自宅デスク環境一挙公開!
-

【連載・視点】横並びの価格設定はしない!有機米栽培を成功させた群馬・浦部農園とは
-

【まちてん】ブランド化した「みかんブリ」って何だ?海の二毛作を実現した新商品
商品自体の歴史は5年ほどだが、ベルサイユ宮殿で行われた晩餐会に採用されたり、高級ファッションブランド「ディオール」のパリ本店で販売されたりと、世界で高い評価を得ている。製造元は、大正10年創業の窯元で、従業員20名ほどの株式会社カネコ小兵製陶所(岐阜県土岐市)。伝統を継承しつつも、新たな視点を取り入れ、キラリと光るものづくりに取り組む伊藤克紀社長に、開発ヒストリーを聞いた。
■廃業の危機が、挑戦の力に
日本有数の陶磁器生産量を誇る岐阜県土岐市およびその界隈でつくられる陶磁器は、美濃焼と呼ばれ、国から伝統的工芸品に認定されている。その窯元のひとつ、カネコ小兵製陶所は、かつて熱燗用の徳利を製造していた。ピーク時の1970年代は、年間160万個を生産し、国内有数の徳利メーカーとしてその名を馳せた。
しかし1990年代に入ると、飲酒習慣の多様化から熱燗離れが進み、生産量は徐々に下降。同業者の多くは廃業した。カネコ小兵製陶所も「1996年から2005年までの10年間で出荷本数が98%ダウン。価格競争も激しくなる一方」というほど危機的状況に。「生き残るには、人をあっと驚かせるような器をつくるしかない」と伊藤社長は、新たな付加価値を生み出すことに挑戦するようになる。
その付加価値のひとつとして伊藤社長の眼に留まったのが、うるし塗りだ。あの独特の光沢と深みを、磁器でどうやって再現させるか。
「理論上では、うわ薬にあめ釉(ゆう)と呼ばれる溶液を配合すれば再現できることは分かっていました。だから先人たちも挑戦してきましたが、成功したという話を聞いたことがありません。ごく稀に成功したとしても、それは偶然だったりします。うわ薬の配合、塗り方、窯の温度調整など、それら何千、何万もの組み合せの中から、たったひとつの法則を導くには途方もない時間がかかります」
どのような作業だったのか。
透明な質感を出すために使用するあめ釉は、漆のような色合いにするとうわ薬が流れやすく、垂れやすくなる性質がある。流れないようにすると漆の質感は出せない。あめ釉の配合が難しく、微妙な調整や顔料の工夫などが必要だったという。次に土との相性だ。あめ釉が配合されたうわ薬は土を選ぶといわれている。土によって垂れ方が変わってしまい、安定した色合いがでない。また窯の温度管理も難しい。温度計だけではわからない変化を見逃さず1300度という適切な温度を保つ必要があるが、内部の正確な温度は天候や季節によって微妙に変わってくるという。この変化は窯の温度計だけを見ていてもわからないそうだ。
それだけセンシティブな素材であるため、当然塗り方も熟練を要する。均一に、垂れないように塗るための技術は職人が肌で覚えるしかない。理論と試行錯誤で開発された「ぎやまん陶」だが、品質の最後の砦は熟練の技が守っている。
■新鮮な驚きを感じてもらいたい
カネコ小兵製陶所もその挑戦に踏み切ったのが2006年。それはモノづくりというより、気が遠くなるような地道な研究の積み重ねだったという。励みになったのは、段階的に設定した目標ごとの成功例。
「最初は数百個に1個が成功しました。まず垂れを抑えることに注力する。次にブク(表面の凹凸)を抑える、ピンホール(針でつついたような穴)を抑える。とステップを踏んだ工夫と開発を続けました。そうするごとに、100個に1個、90個に1個、80個に1個といった具合に成功確率が徐々に上がっていきました。研究開発の長期化は、会社の財務状況を考えると痛いですが、従業員らの士気が高くなったのは救いでしたね。3年かかりましたが、マラソンに例えると、42.195キロの中で、30キロ地点まで走ったら、気持ち的には「あと10キロだ!頑張ろう!」ってなりますよね。倒れそうだけど、そういう感じだったから頑張れたのかなと思います」
めどが付いたのは2009年。うるしのような風合いが出るうわ薬が完成し、量産化の技術も確立できた。デザインはいろいろ試した結果、放射状に広がる菊を象った皿が、最も見栄えがよかった。うわ薬の粘度が従来のものより低いため、凹部分にたまりやすく、それが色の濃淡、光の明暗となって、まるでガラスのような質感となるのだ。
伊藤社長はこの菊の磁器を「ぎやまん陶」と名付けた。「ぎやまん」とはガラス製品の古風な呼び方。江戸時代、ダイヤモンド(金剛石)をそう読んだことが由来とされる。「日本人が初めてガラスを見たとき、ぎやまんのようにきらきら光っていてびっくりしたように、この器を見た人にも新鮮な驚きを感じてもらいたい」という思いを込めた。
カラーは日本古来の藍染を表現した「茄子紺ブルー」、美濃焼の伝統である織部釉を現代風にアレンジした「利休グリーン」、漆器を思わせる深みのある風合いを表現した「漆ブラウン」の3色展開。価格は三寸皿(直径98mm)が850円、六寸皿(直径180mm)が1950円、八寸皿(直径240mm)が3200円(いずれも税別)など。温める程度の電子レンジや食器洗い乾燥機にも対応する。
■ディオールから受注
ぎやまん陶が世界から脚光を浴びるきっかけになったのは2010年2月、ドイツで開かれる世界最大級のインテリア見本市に出展したときのこと。商社を介して「ディオールのバイヤーが、パリ本店でやぎまん陶を扱いたい」という話が舞い込んできたのだ。
フランスを意識して同じ手法でネイカフェ・オ・レボール型も用意したが、ディオール側からいわれたのは「日本という風土、文化の中でできたユニークなものだからこそ取引をしたいと思っている。私たちに迎合する必要はありません」。つまりディオールが欲しいのは、菊を象ったぎやまん陶そのもの。伊藤社長は「意外な反応でしたが、それがかえって自信につながりました」と、自分たちがやってきたことや日本の伝統に改め誇りを感じたという。
ディオールのパリ本店で販売されるようになったぎやまん陶は、フランスの星付きシェフ、ジャン・フランソワ・ピエージュ氏の目にも止まり、2011年、同氏がシェフを務めたベルサイユ宮殿での晩餐会にも採用された。この晩餐会に使われたやぎまん陶は、真っ白の冷菓を一層引き立たせる茄子紺ブルー。その芸術的な存在感は、世界各国のメディアにも紹介されるようになった。こうしてやぎまん陶は、海外にも顧客を持つ主力商品のひとつに成長した。
やぎまん陶の成功によって、商品開発に対する従業員のモチベーションが高まったという。徳利メーカーとして培った“容量を量る器”を作る技術を生かした「100キロカロリー茶碗」、土物の味わいを表現した磁器「リンカ」などを開発、販売。いずれも好調な売れ行きを見せており、特にリンカはやぎまん陶と並ぶ看板商品になりつつあるそうだ。
【地方発ヒット商品の裏側】ベルサイユ宮殿の晩餐で使用された「ぎやまん陶」とは?
《DAYS》関連ニュース
-
 【連載・視点】横並びの価格設定はしない!有機米栽培を成功させた群馬・浦部農園とは
【連載・視点】横並びの価格設定はしない!有機米栽培を成功させた群馬・浦部農園とは
-
 【まちてん】ブランド化した「みかんブリ」って何だ?海の二毛作を実現した新商品
【まちてん】ブランド化した「みかんブリ」って何だ?海の二毛作を実現した新商品
-
 【まちてん】“ガイドブックにない現地体験”で訪日外国人を呼び込む!
【まちてん】“ガイドブックにない現地体験”で訪日外国人を呼び込む!
-
 【連載・視点】海外需要を捉えて成功した日本の伝統工芸……岩鋳の南部鉄器
【連載・視点】海外需要を捉えて成功した日本の伝統工芸……岩鋳の南部鉄器
-
 【視点】ママさん社員のアイデアがヒットに!「マカロンレースマスク」
【視点】ママさん社員のアイデアがヒットに!「マカロンレースマスク」
-
 【視点】三重県の町工場から生まれた「魔法のフライパン」の開発秘話
【視点】三重県の町工場から生まれた「魔法のフライパン」の開発秘話
-
 【連載・視点】合成繊維の技術で作れないものはない!成功を呼び込んだ小松精練の戦略
【連載・視点】合成繊維の技術で作れないものはない!成功を呼び込んだ小松精練の戦略
-
 【連載「視点」】売上げ好調のくら寿司、ライバルはコンビニ
【連載「視点」】売上げ好調のくら寿司、ライバルはコンビニ
-
 【連載・視点】19歳はリフト代タダ!業界を動かしたビジネスモデル
【連載・視点】19歳はリフト代タダ!業界を動かしたビジネスモデル
-
 【連載・視点】秋田美人を産業化する!25歳女性社長の挑戦
【連載・視点】秋田美人を産業化する!25歳女性社長の挑戦