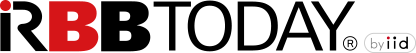年間150万人を集客! 人口3500人の村を変えた「道の駅」の存在
エンタープライズ
その他
しかし、93年の設立以降、道の駅の経営は開業から15年に渡って赤字続きだったという。08年の時点での年間来場者は55万人程度。そこから売り上げ約15億を超える一大観光拠点に成長するまでには、一体何があったのか? 駅長の小海一則氏に話を聞いた。
■株式会社「田園プラザ川場」の誕生
かつて、川場村は農業と養蚕が主産業の旧態依然とした農村だった。しかし、絹糸の需要が低迷する中で、村民の経済状態は悪化。若者たちは次々と村を離れ、71年には国から過疎指定を受けている。
農業を続ける一方で、この村では観光を新たな産業の柱にしなければいけない。新しいスローガンとして「農業プラス観光」を打ち出したのは、当時村長を務めていた永井鶴二氏だった。77年には国鉄からD51機関車を譲り受け、村内にSLホテルを設立。89年には川場スキー場が開業している。
一方で81年には東京世田谷区と相互協力協定を締結。農業体験や小学校の移動教室などで、世田谷区民が村を訪れるようになる。区民と村民の間で交流が進む中、永井村長が訪れたのが区内にある大学だった。村の農産物を直売やアピールするにはどうすればいいか。さらに、村を訪れる人たちとコミュニケーションの場をどのように作ればいいのか。東京農大や東京工大の教授にアドバイスを求めた。
これらの意見を集約する形で立ちあがったのが「田園プラザ構想」だった。建設に必要となる予算は31億円。村の年間財源は約13億円だった頃、村長は県や国の補助金、農水の過疎化対策費、中山間地の整備事業費などを必死にかきあつめたという。最後に全体の6%にあたる2000万円を村が出資し、村が持つ土地を利用して、田園プラザは93年に着工した。
ちなみに、国土交通省が「道の駅」の登録制度を始めたのが、同じく93年のこと。そのため、当初は田園プラザを道の駅にするという構想は無かったという。さらに、事業計画を実現するため、同年に株式会社田園プラザ川場が発足。これら一連の経緯は、後に田園プラザ急成長の一因となっていく……。
■村の9割の農家が集うファーマーズマーケット
川場田園プラザは96年、群馬県では6番目の道の駅として登録される。この頃になると、ミルク工房やミート工房、ファーマーズマーケットといった施設が次々と完成。98年にはビール工房、パン工房、レストラン、物流センターの営業が始まり、ついに道の駅はグランドオープンを迎えた。
しかし、94年にミルク工房の営業が始まって以来、川場田園プラザの収益は厳しい状態が続いていた。村から運営予算を割り当てられて、なお経営は赤字続き。それを村が毎年補てんして、何とか営業を続けていた。
この状況に当時川場村の村長だった関清氏は、川場田園プラザの改革に着手する。具体的には行政指導による株式会社からの脱却。村役場の担当者に任されていた道の駅の経営を止め、民間主導に向けた組織替えを行う。そこで白羽の矢が立ったのが、現社長の永井彰一氏だった。
永井氏は08年に社長に就任すると、まずは全社員を一斉に解雇。その中でも働きたいと名乗り出るものには面接をしながら、外部からも新たな人材を広く集めた。その上で徹底的に行ったのが意識改革だったという。一つは、挨拶から掃除まで、店員としての意識を全職員に徹底させること。そして、もう一つが“地産地消”と“本物志向”というコンセプトだった。
「道の駅を訪れる人の7割は、首都圏にお住いの方々です。地元にはすぐ通える場所にスーパーがあって、野菜から肉まで大抵のものが手に入る。わざわざお金を払って、時間をかけて川場田園プラザにやって来てもらうには、ここでしか手に入らないモノ、食べられないモノが必要でした」
川場田園プラザで最も人気の高いファーマーズマーケットに、永井氏は「輸入物や他県のものは絶対に入れるな」と指示を出した。例えば、定番どころでどうしても取り扱いたい野菜があれば、まずは川場村を探すこと。それでも、見つからなければ周辺の地域を、前橋の青果市場を探すように厳命する。
その効果はすぐに表れた。村の朝採れ野菜が手に入ると口コミが広まり、徐々に集客が増えていった。地元野菜への需要が増える中で、道の駅では商品の仕入れ先にも手を加えていく。それまで付き合いのあったJAの商品を、売り場で取り扱うことを止めた。
その上で、ファーマーズマーケットでは、野菜を納入する農家を徐々に増やしていく。生産者にはバーコードを提供し、持ち込んだ野菜を登録。それがレジを通ると、スマホやパソコンに連絡が届く仕組みを用意した。
「例えば、初物のトウモロコシは人気が高く、午後には売り切れてしまいます。このとき、店では出荷者宛に一斉メールを送るので、生産者は再び野菜を持ち込むことができ、マーケットでも品切れを起こさずに済むわけです」
さらに、完売が確認できれば、生産者は売り物をマーケットから引き上げる必要もなくなる。取引が簡略化されたこともあり、今では420人の生産者がシステムに登録しているようだ。これは、庭先農業も含めて、村で農業に従事している人の約9割におよぶ。
■2億円を売り上げる「飲むヨーグルト」
“地産地消”と“本物志向”。このコンセプトを実現するために、川場田園プラザでは様々な新製品を世に送り出す。最初に動き出したのはミルク工房だった。それまで手掛けていた牛乳やアイスクリームの販売を止め、ブームの兆しが見えていた飲むヨーグルトの開発に着手する。
飲むヨーグルトは当時、周辺の観光地でも販売されていた。その中で独自性を貫くには、どのような商品にすべきか。“本物志向”を追求する中で、川場田園プラザはそれを濃度に求めた。キャッチコピーはそのまま“濃いね”。フレーバーなども用意せず、プレーンの一品だけで勝負する。
「これが今では150mlのボトルに換算して、年間183万本売れるようになりました。定価が125円ですから、それだけで約2億円の売り上げです。最近では『プレミアムヨーグルト』(1800円)を商品ラインアップに加えましたが、こちらも贈答品やお土産として人気を集めていますよ」
一方で飲食店についても、カレーからラーメンまで何でも扱うフードコートのような商売を止め、地元の味にこだわったメニューを提供しはじめる。郷土料理の「おきりこみ」、川場ブランドのニジマス「銀ひかり」をメインに据えた御膳、上州もち豚のステーキやカツ。そば処では土地のそば粉を100%使い、ピザ工房では土地の野菜やソーセージをトッピングした。
ここでしか食べられないモノがある。その噂を聞きつけると、テレビや雑誌などが自然と取材に集まってきた。草津温泉や日光に向かう観光ツアーのプログラムにも取り入れられ、今では多い日に40台を超えるバスが立ち寄るという。
「ただ、我々の取り組みは必ずしもすべてが成功したわけではありません。人気商品ができる裏側で、それ以上の失敗を繰り返しているんです」
例えば、パン工房では以前にドイツをイメージして、ハード系の堅パンを扱っていたことがあるという。しかしこれが全く売れない。そこで、新たに立ち上げたのが、土地の米粉を使った新製品だった。つなぎに群馬特産の大和イモを使うことで、卵とバターを全く使わないパンが完成。これが、アレルギーを持つ人にウケると、テレビ番組でも取り扱われ、今では土日祝は予約販売のみという人気商品になった。
15年にはオープンキッチンのデザート工房を立ち上げ、子供向けの遊具を一か所に集めた広場も完成。軽快なフットワークで常に新しいことに挑戦し続けている。
「私たちは国内でも珍しい株式会社が運営する道の駅です。国土交通省の出資も受けておらず、土地も100%が村のもの。その村長から任された事業ですから、話が決まるのが圧倒的に早いんです」
道の駅の運営形態はNPO指定管理、公社、振興局などさまざまで、役場の退職者が天下って経営をしているところも多い。例えば、バリアフリーのために段差を一つ削るだけでも、地権者に始まって、地元の行政、国土交通省などに書類を出して……ハンコがすべてそろうまでに1年かかるのが当たり前だという。
「県内にある道の駅の連絡会などに行くと、決まって言われることがあります。田園プラザさんは、話が速くてうらやましいね、と」
■駅の人気商品で海外に販路を開く
川場田園プラザには「ジャパン・アジア・ビアカップ」で2年連続の入賞経験を持つビール工房がある。これを売り物に、11年から取り組んでいるのがビールの海外輸出だ。
「村長が交換留学の付き添いで渡米する機会がありまして、その時に現地のバイヤーを回って交渉しました。来年にはヨーロッパにも販路を広げる予定です」
海外輸出に合わせて、工房ではビールの長期保存に着手した。濾過と熱処理を機械化することで、常温で1年間の保証を実現。近年では機械の性能が向上し、職人の腕も磨かれたことで、一定の品質を保つことができた。
今では年間製造量のうち55%を海外に輸出しているという。工房には2キロタンクが11本、1キロタンクが12本あるが、これを毎日2回転させても生産が追い付かない状況だ。実は伊香保温泉の地ビール「石段物語」も、ここで作られたものだという。
また、敷地内には川場スキー場が運営するシャトルバス連絡所があるが、ここで提供しているおにぎりも、15年に海外進出を果たしている。これは、全国米・食味分析鑑定コンクールで8年連続金賞を受賞した、地元名産の「雪ほたか」を使ったもの。ロサンゼルスでは「KAWABA RICE BALL」の名前で売り出したが、米が足りなくなるぐらいの人気になっているようだ。
■川場の観光拠点として村を元気に
川場村では99年に過疎化指定を解除された。近年ではUIターンを希望する人も増え、川場田園プラザでも彼らを毎年のように受け入れているという。一方、野菜の直売先ができたことで農家は力を取り戻し、村内にまばらにあった遊休農地は姿を消した。中には、ドライフルーツやジュースなどを独自に開発する生産者もいるという。
「六次化産業の失敗談をよく聞きますけど、川場の農家はみんな元気にやっていますよ。これはよく言っていることなのですが、製品を作る前に、まず流通先があることが大事なんです。売れる自信があれば、生産者も本気になりますから。パッケージなども自分で印刷所と交渉して、カッコいいものを作っていますね」
永井社長が就任して1年後、川場田園プラザは初の黒字を出した。14年には15億円の売り上げを計上している。川場田園プラザには広報用の予算は一切存在しない。では、なぜここまでの人気を集めたのか? そこで、大きな力を担っているのが、東京世田谷区との相互協力協定だ。これまでに移動教室で川場村を訪ねた小学生と区民は累計185万人。初年度に区立小学校交流事業へと参加した小学生が、今では50歳になった。
「川場村の話をどこかで聞いて、家族で遊びに来たり、口コミで広めてくれる人が一杯いました。ここ数年の急成長は、世田谷区民の方のネットワークがあってこそのものだと思います」
“地産地消”と“本物志向”。それは口に出せば当たり前に聞こえるかもしれない。しかし、その積み重ねが口コミを呼び、マスコミを動かし、今の川場田園プラザがある。
~地元から日本を盛り上げるキーパーソン~UIターン、六次化、遊休農地削減……村を変えた道の駅
《丸田鉄平/HANJO HANJO編集部》関連ニュース
-
 【国際ロボット展】トラクターの“無人化”を実現……ヤンマー「ロボトラ」
【国際ロボット展】トラクターの“無人化”を実現……ヤンマー「ロボトラ」
-
 【まちてん】消滅の危機にある全国の古民家を“村”に!
【まちてん】消滅の危機にある全国の古民家を“村”に!
-
 セキュリティ強化に重きを置いたリモコン式スマートロック
セキュリティ強化に重きを置いたリモコン式スマートロック
-
 乃木坂46高山一実、地元・千葉県を猛アピール!
乃木坂46高山一実、地元・千葉県を猛アピール!
-
 【ビジネスEXPO】生産者をサポートする直売所総合販売管理システム「toreta」
【ビジネスEXPO】生産者をサポートする直売所総合販売管理システム「toreta」
-
 【東京モーターショー2015】実用化はいつ? パーソナルモビリティが続々登場
【東京モーターショー2015】実用化はいつ? パーソナルモビリティが続々登場
-
 岩手県の物産・工芸品の販路拡大へ……東京駅前「KITTE」で復興展開催
岩手県の物産・工芸品の販路拡大へ……東京駅前「KITTE」で復興展開催
-
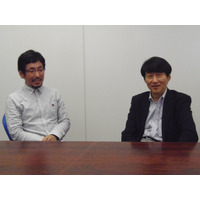 【マイナンバー】中小規模事業者が知っておくべきこととは?
【マイナンバー】中小規模事業者が知っておくべきこととは?
-
 フロント業務の簡略化ができるホテル向けスマートロックシステムが登場
フロント業務の簡略化ができるホテル向けスマートロックシステムが登場
-
 病気療養中だった漫画家の火村正紀さん、6月に死去していた
病気療養中だった漫画家の火村正紀さん、6月に死去していた
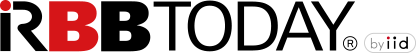





























![映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告映像が公開!川上洋平[Alexandros]&SennaRinによる挿入歌も初披露](/imgs/p/80QnbhSu7Qc8HqNqhlkEqilOSkHtQ0JFREdG/974207.png)