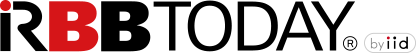キリンホールディングスと東京大学が、スリランカ紅茶農園の環境的インパクトを定量的に確認
※1 絶滅の危機に瀕している生物種
今回は、ドローンを使った3Dマッピング技術と現地調査を統合した手法で調査を実施しました。現地調査では、2012年に発行された「スリランカ国家レッドリスト※2」において、絶滅の恐れがあると指摘されていた種を含む、動植物の生息状況が明らかになりました。それに加え、土地の構造、水の流れ、浸食リスクといった生態系の健全性を包括的に評価しました。具体的な評価結果は以下の通りです。
※2 https://www.cea.lk/web/images/pdf/redlist2012.pdf
<評価結果>
■絶滅危惧種の存在
2012年に発行された「スリランカ国家レッドリスト」において絶滅危惧種とされていた2種の動植物、危急種※3とされていた3種の動植物、準絶滅危惧種※4とされていた3種の動植物が、13年経過した2025年にも生息していることを確認。
■生物種の多様性
176種(植物111種、動物65種)という多様な生物が生息。
■固有種※5の存在
記録された動物65種のうち、12種が固有種。両生類においては6種中5種が固有種。植物111種のうち、4種が固有種。長年にわたり、固有種が外来種の侵略によって置き換わらずに存在し続けていることを確認。
■河畔エリアの役割
紅茶農園の景観を構成する要素の一つである河畔が、高い保水能力を持っていることが明らかになった。湖畔は、湿潤な土壌と植生の状態を維持するだけでなく、絶滅危惧種の生存に不可欠な生息地を提供することで、固有種や絶滅危惧種の存在を支えていることを確認。
※3 絶滅の危険性が高いとみなされる種
※4 近い将来絶滅危惧種に移行する可能性が高い種
※5 分布が特定の地域に限定される種。人間生活による影響を受けやすい一方、地域の生態系において重要な役割を果たしており、生態系のバランスを維持するために不可欠とされる
今回の共同研究の調査により、紅茶農園における生物の多様性が確認されました。また、2012年に発行された「スリランカ国家レッドリスト」において絶滅の恐れがあると指摘されていた動植物種の存在を確認することができ、紅茶農園が地域の生物多様性保全にとって重要な拠点であることを確認しました。
この調査で得られた成果は、TNFD※6とともに参画しているNature Positive Initiative※7(以下、NPI)が主導する、「自然の状態」を測る生態系指標の国際的な標準化に向けたパイロットテストへ活用されます。今後も、紅茶農園を営むことで周囲の生態系にどのような影響をもたらすのかを継続的に調査していく予定です。
自然資本に関連する情報開示の中で、企業は自社のオペレーション範囲のみならず、サプライチェーン上でも自然の状態を測定し、開示することが今後求められると予測されます。サプライチェーンの上流における課題把握のためのトレーサビリティ確保や測定に困難を抱える企業が多い中、当社が上流でこのような調査を実施できる点は世界的にも珍しい事例です。こうした取り組みを通して得られる知見を生かし、今後、生産拠点だけではなく、サプライチェーン全体でのネイチャー・ポジティブの実現を目指していきます。
※6 Task Force on Nature-related Financial Disclosuresの略。自然資本に関するリスクと機会について企業が報告し行動するための、リスク管理に向けた情報開示の枠組みである自然関連財務情報開示タスクフォース
※7 世界最大規模の自然保護団体、研究機関、企業、金融連合27団体が集まり発足した団体。「ネイチャー・ポジティブ」という言葉の定義、整合性、使用に関する調整を推進し、成果をもたらすためのより広範で長期的な取り組みを支援することを目的としている
■キリングループとスリランカのこれまでの取り組み
キリングループは、2007年から農園で働く人や家族、子どもたちの笑顔をサポートするために、教育支援の一つとして図書の寄贈を開始するなど、「キリン 午後の紅茶」に使用される紅茶葉の原料生産地であるスリランカにおいてさまざまな活動を行ってきました。2024年12月には、レインフォレスト・アライアンス(CEO:Santiago Gowland)と共同で2023年10月より開発してきた環境再生型農業※8への移行を促すツールである「リジェネラティブ・ティー・スコアカード」の運用を開始し、土壌の健全性、農園内の生物多様性の保全、生態系の回復、農園の人々の生活向上を促進する方法を提示しました。また、2022年よりスリランカの紅茶農園を対象とした、人権デューデリジェンスの取り組みも行っています。さらに、2025年6月からスリランカ紅茶農園従業員のウェルビーイング向上に向けた共同研究を森川研究室と実施しています。
自然の恵みを原材料に、自然の力と知恵を活用して事業活動を行っているキリングループは、複合的に発生し相互に関連する環境課題(生物資源・水資源・容器包装・気候変動)に統合的に取り組み、豊かな地球の恵みを将来にわたって享受し引き継ぎたいという思いをバリューチェーンに関わるすべての人々とともにつなぐべく、自然と人に「ポジティブインパクト」を与えるさまざまな取り組みを積極的に進めていきます。
※8 農業活動を通じて環境の保全や再生を目指すアプローチのこと
<参考>
・キリングループ環境ビジョン2050 https://www.kirinholdings.com/jp/impact/env/mission/
・キリングループ「環境報告書」 https://www.kirinholdings.com/jp/investors/library/env_report/
■東京大学大学院新領域創成科学研究科 森川研究室とスリランカのこれまでの取り組み
東京大学大学院新領域創成科学研究科の森川想講師の研究グループでは、2010年にスリランカにおける高速道路などの社会基盤事業の現地への影響について研究を開始し、以降15年間にわたり、スリランカの社会とコミュニティに関する研究を現地の研究機関とともに進めてきました。スリランカでは経済的基盤の脆弱性に加えて、2022年に財政危機を経験するなどしていることから、資源の不足に苦しむ政府以外のステークホルダーの積極的な参与が社会的課題の解決において期待されています。当研究グループは、途上国における公共政策の形成・実施を専門として研究する中で、現地の経済社会に対する日本企業の貢献について研究関心をもっており、キリングループのCSV活動とその成果の詳細な検討を行うという今回の問題意識に賛同し、共同研究に参画しています。当研究を通じて、新興国の社会におけるウェルビーイングの測定や、日本と現地の企業が主導する環境保全のあり方について学術的知見を活用・蓄積することを目指します。
東京大学大学院新領域創成科学研究科は、「学融合」を基本理念に教育・研究を行うことを目的に、修士・博士課程のみの大学院部局として 1998 年に新設されました。学融合を通じて新たな学問領域の創成を目指し、現代社会の要請とその変化に対応して、人類が解決を迫られている課題に果敢に挑戦するとともに、領域横断的な視点と高度な問題解決能力を有する国際性豊かな人材を育成し、より良い社会の実現に積極的に貢献していくことを教育研究の目的としています。
<参考>
・東京大学大学院新領域創成科学研究科ウェブサイト https://www.k.u-tokyo.ac.jp/
企業プレスリリース詳細へ
PRTIMESトップへ