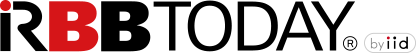株式会社Integral Geometry Science(以下「IGS」)は、X線では検出できない自己放電箇所を特定する微短絡特定技術を開発しました。本機器を2025年9月17日(水)~19日(金)に幕張メッセにて開催される「BATTERY JAPAN 二次電池展 」に出展します。さらに9月18日(木)14:30~15:00に、神戸大学数理・データサイエンスセンター教授 兼 IGS 代表取締役 木村建次郎がセミナーに登壇し、本システムについてご説明します。
航空機や電車内でのモバイルバッテリーの発火、EVの発火など蓄電池の安全管理が問われています。蓄電池の発火の原因は、基本的には内部の短絡ですが、そもそも良品、不良品に関わらずあらゆる蓄電池に自己放電は生じています。つまり、充電後、永遠に電気を蓄え続けることができる電池は存在しません。自己放電が生じる根幹的理由は、電池のサイズが有限であること、電池内部に空間的不均質、不均一性が存在することです。この不均一性の極端な状態が内部短絡であって、そういった意味ではあらゆる電池が発火の危険性はゼロではないということになります。不均一性の大きな電池では、内部で電界の集中が生じ、結果としてイオン濃度の局所異常を生み出し、短絡原因微結晶の析出を誘導します。この不均一性をいかに出荷前に評価するかが、安全性向上に寄与することになります。
空間的不均一性を直接的に評価する方法は画像診断技術です。画像診断技術の空間的分解能を考慮すれば、すぐに短波長電磁波であるX線を想定されますが、今の場合、この選定は極めて大きな誤りです。この誤りを一言で表現すると、「“磁化した鉄棒”と、“磁化していない鉄棒”をX線で識別することは極めて困難」となります。この困難さは、ダイナミックレンジという言葉を用いても説明されます。ダイナミックレンジというのは、計測器も動物の目も眩しい光が入射して場合は、ほかの少々のものは見えなくなってしまいます。太陽が照りかざす真昼には、他の星をみることはできません。この感覚をもって、ダイナミックレンジという言葉が理解されます。つまり、いくら短波長の電磁波を用いたとしても、集電体や活物質など様々な物質が複合的に存在する電池内部において、マイクロアンペアの自己放電に対応する、マイクロメートルスケールの軽元素リチウムの微結晶を検出、映像化するためには、現実的ではないダイナミックレンジが必要となります。つまり、画像診断を考慮する場合には、空間分解能とダイナミックレンジの双方のバランスのなかに、最適解が存在します。
上の誤りに気付けば、どのような電磁場を観測に用いればよいか自明です。 “磁化した鉄棒”と“磁化していない鉄棒”を区別する方法は、方位磁針を近づけることです。しかしながら、方位磁針が測定する磁力線と電池内電流の関係には、電流磁場逆問題の解くという大きな壁が存在しています。
これまで当社は、蓄電池外部に漏洩する磁場の空間分布の測定結果から、蓄電池内部の電流密度分布を解析的に導き映像化する、蓄電池内部電流密度分布映像化システムの開発に世界で初めて成功し、実用化してきました。本機器を用いることで、従来のエージング試験で良品と判断された電池群に含まれる、潜在的不良品を抽出することが可能になります。図1に示す28個のデータは、本機器で得られた良品の電流密度分布画像です。これらの画像の電流集中箇所とサイクル試験の相関を精査した結果、電流局所集中の大きい蓄電池の寿命がほかの電池と比べて著しく寿命が短いことが確認されました。

図1 出荷された良品における蓄電池内部電流密度分布画像。画像中、黒は電流密度が小さく、青から緑、赤と電流密度が大きいことを示す。
本展示会では、機器の詳細に加えて、適用事例について広くご紹介します。
【「BATTERY JAPAN 二次電池展」出展概要】
期間 :2025年9月17日(水)~19日(金)時間 :10:00~17:00
会場 :幕張メッセ 展示ホール4(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)
ブース番号:E3-30
展示内容 :本機器のデモ機を展示します。
展示会URL:https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bj.html
【セミナー登壇について】
日時:9月18日(木)14:30 - 15:00
場所:5-B:次世代電池 セミナー会場
登壇者:神戸大学数理・データサイエンスセンター教授 兼 IGS 代表取締役 木村建次郎
タイトル:「相次ぐ電池の発火、新しい出荷前画像診断技術 -電流画像可視化- により発火を防ぐ ―X線では検出することができない自己放電箇所特定、微短絡特定技術―」
【株式会社Integral Geometry Science(IGS)について】
IGSは、いままで誰もみることができなかった隠された世界を撮影するテクノロジーを研究開発・事業化する会社です。未知の世界を撮影するためには、外の世界から波動を送り込み、内部で跳ね返りを繰り返し外の世界に漏れ出た波紋を観測し、映像を創りだす必要があります。この作業は、波動散乱の逆問題とよばれ、極めて困難な応用数学史上の未解決問題とされてきました。木村建次郎博士および木村憲明博士は、2012年にこの問題を世界で初めて解くことに成功、「散乱の逆問題の解法及び画像化法」が日米中欧 世界各国で認められ、特許を取得しました。この研究成果を社会実装するため、2012年にIGSが設立されました。同社は神戸大学インキュベーションセンターに研究開発拠点を置き、透視技術の研究開発と実用化に取り組んでいます。ホームページ:https://www.igs-group.com
企業プレスリリース詳細へ
PRTIMESトップへ