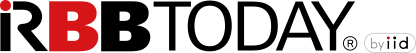~AIを活用した技術革新と、未来のモビリティを取り巻く環境に向けた新たな価値創出を加速~
発行:2025年8月8日
住友ゴム、北海道大学に共創型研究拠点を開設
~AIを活用した技術革新と、未来のモビリティを取り巻く環境に向けた新たな価値創出を加速~
住友ゴム工業株式会社(社長:山本悟)は、このたび国立大学法人北海道大学(総長:寳金清博)の総合イノベーション創発機構データ駆動型融合研究創発拠点「D-RED」※1内に、新たな研究拠点「住友ゴム イノベーションベース・札幌」を開設します。
住友ゴムの研究者と北海道大学の研究者・学生が協働し、実世界で自律的に判断・動作するフィジカルAI※2など先端技術の研究と実用化に取り組み、ものづくりの未来を切り拓く技術革新を推進してまいります。また、未来のモビリティを取り巻く環境を見据えた新たな社会的価値の創出にも挑戦します。住友ゴムはこれらの取り組みを通じて、長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」の達成に向け、競争力のさらなる強化と技術・社会両面にわたるイノベーション創出を目指してまいります。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508063306-O1-E0Rk9JS3】
1.背景
近年、製造業を取り巻く環境は急速に変化しています。労働人口の減少や技術伝承、カーボンニュートラルへの対応など、製造業が持続的な成長を遂げるためには、未来を見据えた挑戦と変革が欠かせません。なかでも、自動車業界においては、EV化や自動運転の進展、地域交通の再設計など、人々の生活そのものが大きく変わろうとしています。
このような背景のもと、住友ゴムと北海道大学は「住友ゴム イノベーションベース・札幌」の開設を決定しました。ゴム・高機能材料の研究開発に強みを持つ住友ゴムと、画像・映像認識や動画解析に強みを持つ北海道大学が、企業と大学の枠を越えた共創により、未来のモビリティを取り巻く環境を共に切り拓く挑戦を進めてまいります。
2.価値創出のビジョン
住友ゴムは「R.I.S.E. 2035」実現に向けた成長促進ドライバーの一つとして、「ゴム起点のイノベーション創出」を掲げています。これは、ゴムの可視化技術を人材育成・強化や外部連携で向上させ、新たな体験価値を生み出す高機能ゴムを開発する取り組みです。
その実現を支える重要な技術の一つがフィジカルAIです。住友ゴムは、この技術を活用することで、人とAI、それぞれの強みを最大限に発揮し、未来のものづくりの可能性を広げてまいります。
今回設置した「住友ゴム イノベーションベース・札幌」は、まさにこのフィジカルAIなど先端技術の実用化と未来のモビリティ社会への新たな価値創出に向けた研究拠点です。ものづくりの現場から生まれる新たな研究テーマをもとに、AI技術の検証・実装に取り組むとともに、未来のモビリティ社会に資する新たな技術や価値の創出にも挑戦してまいります。
さらに、学生の皆さんには、企業のリアルな研究テーマに触れ、社会実装を見据えた自由な発想を発揮する機会を提供するとともに、住友ゴムの社員にとってもこれまでにない新たな視点や発想を得ることで、イノベーションを担う人材の育成に取り組んでまいります。
住友ゴムと北海道大学は共創を通じて、未来のものづくりと新たな社会的価値の創出を目指します。
【D-REDでの活動概要】
(1)名称: 住友ゴム イノベーションベース・札幌
(住友ゴム研究開発本部 先進技術・イノベーション研究センター)
(2)活動内容:フィジカルAIなど先端技術の研究・開発と未来のモビリティを取り巻く環境における共創活動
(3)運営体制:
住友ゴム工業株式会社
研究開発本部 先進技術・イノベーション研究センター 課長 兼
北海道大学総合イノベーション創発機構データ駆動型融合研究創発拠点
客員准教授 三好 和加奈
北海道大学
副学長/総合イノベーション創発機構データ駆動型融合研究創発拠点長/大学院情報科学研究院 教授 長谷山 美紀
大学院情報科学研究院 教授 小川 貴弘
大学院情報科学研究院 准教授 藤後 廉
(4)設置場所: 北海道大学総合イノベーション創発機構データ駆動型融合研究創発拠点(D-RED)内
3.今後の展開
住友ゴムとして異分野融合によるイノベーション創出を目指す研究拠点の設置は、2023年に宮城県仙台市に開設した「住友ゴム イノベーションベース・仙台」に続く2拠点目となります。
今後はさらに、企業・自治体・研究機関など多様なパートナーとのオープンイノベーションを推進し、共創型の研究開発エコシステム※3の構築と持続的な競争力強化・価値創出に努めてまいります。
4.両者コメント
住友ゴム工業株式会社
当社では長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」のもと、「ゴムから生み出す“新たな体験価値”をすべての人に提供し続ける」ことを目指しています。この戦略の一環として新たな領域への挑戦を進めています。今回、画像・映像認識や動画解析で最先端の技術を持つ北海道大学様と協働できることを大変喜ばしく思います。今後は「住友ゴム イノベーションベース・札幌」を活用し、当社のパーパスである「未来をひらくイノベーションで最高の安心とヨロコビをつくる」を実践していきます。
北海道大学
北海道大学は1876年の創基以来、学際的な研究を推進しており、2026年に創基150周年を迎えます。データ駆動型融合研究創発拠点(D‑RED)では、画像・映像認識やサイバーフィジカル解析を専門とする教員が参画しており、多様なデータを活用した融合的研究を展開しています。このたびの住友ゴム工業との連携では、当該分野の高度な専門性を活かし、安全かつ持続可能なモビリティ社会の実現に向けた実証と社会実装に取り組んでまいります。
<ご参考>
・長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」 https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2025/sri/2025_014.html
※1 「Data‑Driven Interdisciplinary Research Emergence Department」の略で2022年7月、北海道大学副学長・長谷山美紀を拠点長として設立。札幌キャンパス内に拠点を構え、「データ×異分野融合」による共同研究ユニットの組成、産学官連携による社会実装やスタートアップ支援などを通じて、地域課題の解決と大学全体のデータ駆動型研究体制強化を推進する中核拠点。
※2 人工知能(AI)がセンサーやロボットなど実世界の装置と連携し、物理空間において自律的に認識・判断・行動する技術。
従来のAIが主にデジタル空間での分析・予測に活用されていたのに対し、フィジカルAIは認識結果を実際の「動作」や「制御」へとつなげる点に特徴がある。人手不足や作業の自動化、安全性向上といった現場起点の社会課題に対して、実用的かつ継続的な価値提供が期待されている。
※3 企業、自治体、研究機関などが連携し、技術革新を促進する仕組みや環境のこと。
以上