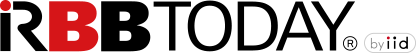また議事録を普通に読めば「中国軍が台湾併合の際に台湾海峡を封鎖し、なおかつその封鎖を戦艦を使って行い、なおかつ米軍が封鎖を解くために来援し、中国がそれを防ぐために新たな武力行使を行った場合、日本にとっては存立危機事態になりうる」至極当たり前のことしか書いていないのだが、野党の議員にはそれらを読み解く読解力が備わってはいないらしい。

<写真:講演する中国駐大阪総領事の薛剣氏=10日午後、大阪市中央区(須谷友郁撮影)産経ニュースより引用>
国会で見解示した高市首相
現在の緊張は、7日の衆議院予算委員会での質疑応答から始まった。野党議員からの「台湾をめぐる状況で、いかなるケースが日本にとって『存立危機事態』にあたるのか」という核心を突く質問に対し、高市首相は以下のように明確に答弁した。
「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」
「存立危機事態」とは、2015年成立の安全保障関連法に基づく法的用語であり、同盟国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かす場合、自衛隊が集団的自衛権を行使して出動できることを指す。高市氏の発言は、これまで避けてきた台湾問題への対応について、日本政府が初めて具体的かつ踏み込んだ法的根拠を示唆したものとして、極めて重要である。

写真;高市総理
中国総領事による「首を斬る」暴力的な恫喝
この高市氏の発言に対し、中国政府は激しく反発。中国外務省は「まったくひどい」と評する一方、さらに驚くべき事態が発生した。
中国の薛剣・駐大阪総領事が8日、自身のX(旧Twitter)アカウントで、高市氏の国会発言に関する報道記事を引用し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」と、公然と暴力的な恫喝とも取れるコメントを書き加えたのだ。
日本の木原稔官房長官は10日の記者会見で、薛氏の発言の趣旨は「明確ではない」と断りつつも、「極めて不適切」だと厳しく批判。日本政府は、この総領事の常軌を逸した投稿について中国側に抗議した。
薛氏の投稿はその後削除されたが、この一連の「とげのあるやりとり」は、中国の外交官が持つ常識と品位の欠如を浮き彫りにしたと言えよう。

写真:中国の薛剣駐大阪総領事 時事ドットコムより引用
国内の「親中勢力」に透ける判断の欠如
一方で、この毅然たる答弁に対し、日本国内の「親中派勢力」とされる勢力、とりわけ立憲民主党の政治家をはじめとする野党幹部からは、発言の「謝罪」と「撤回」を求める声が上がった。
高市氏の発言は、議事録を精査すれば「中国軍が台湾海峡を封鎖し、米軍がこれを解くために出動、中国がそれに対し武力を行使した場合」という限定的な前提に基づいた「存立危機事態」の法的可能性を述べたに過ぎない。これは安保法制の枠組みを考えれば至極当然の論理である。野党議員がその文脈を無視し、感情的な「謝罪要求」に終始することは、極めて政治的な意図が透ける行為であり、議論の成熟を欠いていると言わざるを得ない。
中国の露骨な抗議に直面して即座に発言を撤回することは、「中国の圧力に屈する日本」という極めて負のメッセージを国際社会に送ることと同義であり、外交判断として論外である。仮に撤回に踏み切れば、高市内閣の支持率は地に落ち、日本の外交的信用は失墜するだろう。

写真;トランプ大統領 ロイター通信より引用
日本が挑む「あいまいさ」の壁と残された課題
高市首相は10日、中国側の抗議に対し、発言の撤回を断固として否定し、「政府の従来の見解に沿ったもの」として正当性を主張した。
この問題の背景には、日中間の歴史的な軋轢に加え、台湾の主権をめぐる長年の「戦略的あいまいさ」がある。高市氏の発言は、このあいまいな立場からの脱却を意味する。
中国外務省は、高市氏の発言を「中国の内政への乱暴な干渉」だと批判。林剣副報道局長は10日の記者会見で、「台湾は中国の台湾だ」と強弁し、日本に対し、「日本の指導者は『台湾独立』分離主義勢力にどんなシグナルを送ろうとしているのか」と、事実上の内政干渉の停止を要求した。
最後に、今回の発言が同盟国である米国のトランプ政権との連携を伴わない「フライング」ではないかという、一部の慎重派からの懸念も存在する。確かに、同盟国間の綿密な調整は不可欠である。しかし、台湾有事において、米国が動けば日本が「存立危機事態」に陥るのは、地政学的・法的に見て「普通の感覚」である。高市発言は、この当然の事実を公の場で確認し、中国の過度な覇権主義に対し、日本が明確なレッドラインを引き始めた歴史的な一歩として評価されるべきではある。
欧州ジャーナリスト連盟(European Federation of Journalists)
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
(社)モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助
d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント
KANAME YAGIHASHI
Tatiana Ivanovna
HINATA TARUTANI
配信元企業:一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ