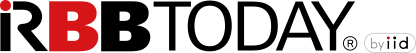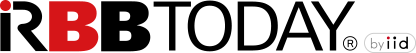擁護が成り立つ話なのだろうか。
これまで無数の芸能人が不祥事で糾弾され、放送界から姿を消した事例は数え切れないほどあるのに、なぜか俳優チョ・ジヌンに対してだけ擁護論が起きている。
独立運動家や“正義の刑事”といった象徴性のある役を演じてきたことが、逆差別のような形で作用していると解釈できるだろう。
擁護論の核心となる論理は、「彼は少年犯として罪をすべて償った」という点だ。少年法が“教化と更生”を目的としていることから、判決文に学校名すら残さないという点を盾にしている。
30年前の過ちを掘り返すことが、はたして国民の知る権利にかなうのかという批判も続いている。結局のところ、非難の矛先が罪を犯した俳優本人ではなく、遅れて判決文を公開したメディア側へ向けられている形だ。
たしかにメディアにもセンセーショナルな報道をした側面はあるが、これはあくまで“その次の話”だ。本当にチョ・ジヌンが擁護すべき対象なのか、そこを検討しなければならない。

チョ・ジヌン以外にも、多くの芸能人が校内暴力やMeToo問題で大衆の前から姿を消した。罪が明確に立証されていなくても、疑惑だけで活動が止まったケースも少なくない。彼らを抱擁しなかったのに、今になってチョ・ジヌンを擁護するというのは、到底公平性に合わない。
チョ・ジヌンの“退場”を主張する側の立場は、「更生して正しく生きるな」という話ではない。“芸能人”という職業的特性を考慮すべきだということだ。
避けようがなく、イメージを伝播する職業であり、テレビや映画を通じて顔がさらされる立場である。あえて犯罪歴のある人物が、不特定多数に影響を与える仕事を担う必要はない。どれほど法的処分が終わったとしても、社会的責任が消えるわけではないからだ。
無理に俳優という職業を続ける理由はない。本人が表に出していないだけで、チョ・ジヌンの被害者は今もトラウマの中で生きている可能性がある。被害者を中心に事案を見れば、到底受け入れられない。証拠が出ていないからといって、被害者の苦痛が消えるわけではない。
謝罪の機会は何度もあった。数年前、メディアが同じ件で事務所に疑惑を提起した際、チョ・ジヌンは今の状況を予見できたはずだ。当時、彼は「そんなことはない」と言って押し通したと伝えられている。
自ら犯した罪を知らなかったわけでもないのに、隠して耐え、最終的に爆発した形だ。作品出演を減らして負担を最小化している間に、自ら罪を認めることもできた。国家が求める象徴的な役割を拒むこともできた。
ファンを欺き、業界を軽視した。詳しい説明もなく、逃げるように引退を宣言した点も、ファンへの敬意が足りないと映る。
事件が知られた後、チョ・ジヌンが反省や悔悟を示したことは一度もない。結局、“チョ・ジヌン・リスク”を背負わなければならないのは、彼を信じた『シグナル』シーズン2の制作陣だ。
にもかかわらず、「誰よりも撮影現場に早く来て周囲に気を配った」などの美談や、「無能な最高裁判事だって自分の席を守ろうとしているのに、なぜ芸能人だけ厳しくするのか」という感情的な擁護論まで出てきている。少年司法の原則を前面に出し、「更生した俳優を抱擁しよう」という主張もある。
しかし、これは本質をぼやかす議論だ。
冷静に見れば、チョ・ジヌンは重犯罪に手を染めた“少年院出身”であり、飲酒運転歴もあり、大人になってからも暴行事件を起こした人物だ。わずか10数年前まで、複数の共演俳優やスタッフに手を上げた疑いがあるという指摘も出ている。更生したとは解釈しがたい部分だ。
このような俳優を擁護することは、どのような名分を掲げても説得力を得るのは難しい。
寛容と包容が必要な社会である。過度な嫌悪的態度への警戒も必要だ。しかし、その前に“公正と公平”が不可欠だ。誰かはチョ・ジヌンより軽い罪でも、芸能界に足を踏み入れることすらできなかった。
チョ・ジヌンへの擁護論自体が、特別待遇であり逆差別だ。無理に俳優をしなくても生きていける。「自分が好きな人だから」と罪の重さを軽くしようとする奇妙な欲望は、むしろ耐えがたい。
◇チョ・ジヌン プロフィール
1976年4月6日生まれ、本名チョ・ウォンジュン。2004年の映画『マルチュク青春通り』でデビュー。以降、『悪いやつら』(2012)、『最後まで行く』『バトル・オーシャン 海上決戦』(2014)、『お嬢さん』(2016)、『毒戦 BELIEVER』(2018)など幅広いジャンルの映画に出演してきた。また、人気ドラマ『シグナル』(2016)の刑事イ・ジェハン役としても知られる。
■「性暴力事件に関与」少年院送致も? チョ・ジヌン、過去の犯罪歴報道が波紋