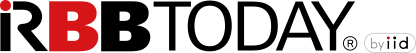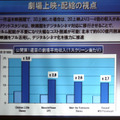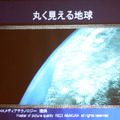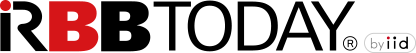【ケーブルテレビショー2010 (Vol.12)】2010年は3D元年――デジタルメディア評論家 朝倉怜士氏
ブロードバンド
テクノロジー
-

【デスクツアー】真似したい自宅デスク環境一挙公開!
-

【ケーブルテレビショー2010 (Vol.11)】最新3D映像技術の現状と問題点――NHK放送技術研究所 奥井誠人氏
-

【ケーブルテレビショー2010(Vol.8)】ホームネットワークの活用提案――パイオニア
朝倉氏は、2010年を3D元年として、そこに至る過去の歴史を振り返るところから話を始めた。まず、映像の歴史における第1の波はモノクロからカラーになったこと。第2の波はSD映像がハイビジョンであるHD映像になったこと。そして第3の波はHD映像が3D化したことにあるという。
3D映像技術そのものは、赤・青のメガネによるアナグリフ方式の映像は1853年から存在し、その後も各社が様々な3Dテレビや映画を発表しているが、普及やビジネスという点では、どれも成功したものはなかった。しかし、2010年はこの3か月前後で、国内主要メーカーが3D対応テレビを発売し、米国の映画は2010年だけで31タイトルが3D作品として上映されるという。3D対応映画館も米国で2009年で4,000スクリーン以上、日本でも350スクリーン以上とされる。
このように急激に3D市場が拡大した理由は、これまでの3D技術が未熟であり制限も多かったが、近年のデジタル技術がHDの解像度で臨場感のある画像が再現できるようになったこと、映画の配給コストが下がるということでデジタル化が進んだこと、それに、高品質な3D作品は多少高い値段でも集客ができ、劇場の収入増につながることなどをあげた。不況やメディアの多様化で劇場から離れた顧客を呼び戻すことができるとして、映画界が3D化に力を入れている現状を説明した。
なお、朝倉氏によれば、3D映画の転換期は2005年とし、その理由は、ディズニー映画の「チキン・リトル」(05年公開)が、品質の点でそれまでの3D映画と一線を画し、この年の「SHOWWEST」にてスピルバーグら著名な監督陣が「これからは3Dだ」と宣言し、娯楽や作品として3D映画の製作が始まったことだとした。
そして、家庭への3Dの浸透だが、この成否のカギを握るのは「エコシステム」だという。つまり、3Dコンテンツの充実、コンテンツを届ける流通・配信網の整備、再生機器・環境の整備が揃う必要があるとした。コンテンツは映画、テレビ番組、ゲームなどの3D化が進み、流通については、デジタルシネマの配給、Blu-rayなど民生向けメディア、3D放送などだ。再生環境は3D対応映画館や3Dレディテレビ(対応テレビ)だ。これらは、さまざまなプレーヤーによってまさにエコシステムが作られているところだ。過去の3Dテレビや映画のように孤立した機器や作品ではないソリューションが、今後の3Dビジネスのポイントとなるということだ。
3Dの映像方式だが、Blu-rayディスクは右眼用、左眼用の信号がともにフルHD(1,920×1,080)で、MVC圧縮という方式が有望ではないかとした。この方式ならフルHD画像ながら、片方の信号を2D画像の差分情報だけにすることで2D画像の1.5倍程度のサイズでフルHDの3D信号をエンコードできるからだ。しかも、元になる2D信号を保持しているため、3D非対応の再生機器との互換性も確保しやすいというメリットもある。
3D放送は、ハーフHD(960×1,080)のサイドバイサイド(画面の左右に2分割して3D化する)を既存帯域で行う方式が当面主流となるが、将来的には、2D信号に奥行き情報(Depth)をエンコーディングする方式でフレームシーケンシャル方式(画面分割なし)の放送が可能になるだろうとした。また、MVC方式の効率がさらに上がれば、フレームシーケンシャル方式でフルHDサイズのBlu-rayコンテンツの3D放送が可能になる。
技術的な問題やエコシステムが整備されるとして、一般家庭に3Dが本格的に浸透するには、コンテンツも重要である。朝倉氏は、すべての映像が3Dに向いているとは限らないので、単純にコンテンツを3D化するのではなく、ジャンルや内容によって使い分ける必要があるとした。3Dに向いているコンテンツとして、映画、スポーツ、ライブ、アイドル、教育などを挙げた。そして、それぞれのジャンルの中でも3Dの効果が高い画像や内容があるので注意が必要だそうだ。
たとえば、現在開催中のサッカーワールドカップだが、フィールドをロングて撮ったような映像は3D化してもあまり感動はないが、フリーキックやセットプレーのようなアングルはまさにその場にいるような臨場感が味わえ、3D化する意義があるとした。そして、スポーツ番組は、中継しながら3D化しやすいので、撮影後の2D3D変換の手間が少ないメリットもある。
映画についてはアニメは3Dとの親和性が高いが、実写ものは実は難しいそうだ。3D映画でヒットした「アバター」は、3D酔いや頭痛、めまいなどの健康上の問題も指摘されている。台湾では観賞中の男性が死亡したという報道もある。実写映像を3D化するときの難しさは、実体験の映像との違和感が出やすいこと、シーン切り替えなどが目に負担をかけることなどによるそうだ。
逆に3Dに向いていない映像、あるいは悪い3Dコンテンツとしては、3D効果を意識しすぎた飛び出す映像は視聴者を疲れさせるだけでありNG。そのほか、書き割り感の出やすい映像、パン・ズームが頻繁に繰り返される、視点がカットごとに違う、デモ画像にありがちな過剰な色対比がある映像などだそうだ。つまり、3Dコンテンツ製作にあたっては、それと意識した撮影、編集、効果を考えなければならないということだろう。
最後に、3Dのアプリケーションについては、ゲーム、パブリックビューイング(街頭TV)、ファッションショー、音楽ライブ会場のモニター、デジタルサイネージ、医療機器や治療支援ツール、教育コンテンツなどの可能性を示し、注意事項としては、体質そのほかで人口の1割程度は3D映像を認識できない人がいること、5歳までの幼児には3D映像は厳禁であることを述べて講演を終えた。