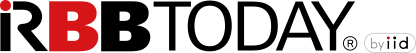単純な意味とのつながりから実践で使える柔軟な単語力へ
2025年7月8日
早稲田大学
東北大学
語彙の知識を洗練することで、より流暢な英語に 単純な意味とのつながりから実践で使える柔軟な単語力へ
記事の詳細は早稲田大学HPをご覧ください。
【発表のポイント】
● 英語を母語としない人が英語を正しく聞き取るためには、「文脈の中で、文全体の意味と単語の組合せの適切さを考慮しながら素早く正確に単語の意味を引き出せる」(=語彙知識が自動化されている)ことが重要です。本研究では、この「自動化された語彙知識」が、流暢に話す力にも強く関わっていることを明らかにしました。
● 一方で、英単語とその意味を一対一の知識として単純化して覚えていること(例:give「与える」)は、発話の流暢さにはあまり寄与しないことが明らかになりました。
● 音声で認識する語彙知識と言語習得の理論的なつながりが明らかになることで、文字情報から学ぶことの多い日本の教育へ新たな知見をもたらす可能性があります。
第二言語(母語以外の習得言語)における語彙の豊富さは、発話の流暢さにとって重要であることがすでに明らかとなっています。しかし、従来の語彙力の測定方法の多くでは、単語単体での意味を知っているかどうか(例:give「与える」)を語彙知識としており、実際の言語使用場面での応用可能性には限界がありました。
本研究グループでは、自動化された語彙知識が単語と意味の一対一の語彙知識と比べて圧倒的に流暢さと関連することを明らかにしました。また、自動化された語彙知識は、学習者の言語知識の豊富さや処理能力と深く関わるとされる発話中の節内で発生する沈黙の数※1と特に強い関連を示すことが分かりました。以上の結果から、最終的には語彙知識を自動化する段階までに洗練させていくことが発話能力にとって重要であることが示唆されました。
本研究は、早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程5年の瀧澤嵩太朗(たきざわこうたろう)、ロンドン大学教育研究所教授、及び東北大学大学院国際文化研究科ディスティングイッシュトプロフェッサーの斉藤一弥(さいとうかずや)、ロンドン大学教育研究所、及び東北大学大学院国際文化研究科研究員の鈴木田優衣(すずきだゆい)、東北大学大学院国際文化研究科ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサーの内原卓海(うちはらたくみ)らで行い、オックスフォード大学出版局発行の学術誌「Applied Linguistics」に2025年7月7日にオンライン公開されまました。
論文名: Automatized phonological vocabulary knowledge as L2 cognitive fluency: Testing the declarative–automatized integrative model in L2 speech production
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507071777-O2-AO6OJr5p】
図 自動化語彙知識を測るテスト
(1)これまでの研究で分かっていたこと
第二言語の語彙習得研究では、多次元モデル※2が語彙知識を理解するための枠組みとして広く使われてきました。このモデルの中で最も大事な要素とされるのが「単語と意味のつながり」であり、多くの研究では、比較的簡単に実施できる単語と意味の一対一のつながりを問うテスト形式を繰り返し使用してきました。しかし、現実の場面では、ある単語を適切に使うためにはその単語の意味が分かるだけでは不十分です。どのような語の組合せで、どのような文脈で使われるのが適切なのかを素早く記憶から引き出せるほどに、その単語への知識が十分洗練(=自動化)されている必要があります。これまでの研究にて語彙知識の自動化を測定する手法が開発され、リスニング能力との関連が示されています[1] [2]。
一方、第二言語における語彙力は、発話の流暢さとも関連があることが近年明らかになっています。その理由の一つとして、発話生成※3の過程では言語処理の段階において語彙の活性化が最初に行われるという点が挙げられます。発話生成の言語処理段階では、語彙の活性化のほかに、文法や音韻の処理も行われますが、これらの知識量や処理能力が十分に発達していないことでつまずく学習者が多く、その結果、発話中の節内において沈黙が発生することが分かっています。
(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
本研究グループでは、語彙知識が自動化されているほど発話生成の効率さが増し、速く淀みなく話すことができ、特に発話中の節内で発生する沈黙において、語彙知識が自動化されていることの恩恵が大きいのでは、と考えました。
この仮説を検証するため、英語を第二言語として学習する日本人大学生210人に対し、二種類の語彙テスト、認知能力テスト、そして二種類の発話課題を行いました。本研究は自動化語彙知識とリスニング能力の関連を調査するプロジェクトの一部であり、語彙テストは先行研究[1][2]で開発されたものを用いました。
二種類の語彙テストは、TOEICの模擬リスニングテストの書き起こしコーパス※4を元に、全部で80個の重要な語彙を選定し、そのうち70%を英語で最も頻出する3,000語以内になるようにしました。一つ目のテストは従来の多肢選択方式の語彙テストであり、英単語を聞いて日本語での意味を四つの選択肢から選びます(図1左)。一方、自動化語彙知識を測る新しいテストでは、単語が含まれる英文を聞いて、文の意味的な適切さを「適切・不適切」の二択で回答します(図1右)。英文は、複雑な構文や文法を避け、テスト項目の語彙以外の93%が英語で頻出する1,000語レベルの簡単な単語で作成し、各語彙がそれぞれ適切な文と不適切な文に入ることで160個用意しました。文の適切さについては、曖昧性を排除するため、「適切・不適切」にはっきり分かれるかを英語母語話者に確認しました。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507071777-O3-8VG92p70】
図1:従来の測定方法による語彙テストのPC画面(左)と自動化語彙知識を測るテストのPC画面(右)
発話課題の一つ目は、8コマの連続した絵を見て順番に描写する課題であり、二つ目は与えられた設問に自由に答える課題を実施しました。発話の流暢さは、自動註釈・自動指標算出システム[3]を使用し、(1)話す速度、(2)節内の沈黙数(3)節外の沈黙数、の三つを計算しました。最後に、認知能力として発話の流暢さと関連があるとされている短期的な記憶力を測定するテストを実施し、分析に含めました。
分析の結果、従来の方法で測定した語彙知識では流暢さとの統計的に有意な関連は見出せず、流暢さに対して0.1%〜0.8%と非常に弱い関連を示しました(図2右)。一方で、自動化語彙知識は流暢さのそれぞれの側面と有意な関連を示し、従来型語彙知識と比べて2.8%〜10.7%と強い関連を示しました(図2左)。特に、自動化語彙知識は節内の沈黙数との関連が強いことが明らかになりました。節内の沈黙数は、発話者の言語知識の豊富さや言語処理速度の速さを表しているとされており、これはまさに、自動化語彙知識が発話生成における言語処理と深く関わっていることを示す結果です。
また、二つの発話課題のうち絵を描写する課題では、絵を描写するための語彙を知っていることが求められるため、より語彙知識に負荷がかかるとされています。テストの結果、自動化語彙知識と節内の沈黙数の関連は絵描写課題においてより強く見られました。このことから、自動化された語彙知識を持っていることで、発話中に語彙でつまずくことが少なくなり、より流暢に話せるものと考えられます。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202507071777-O4-376rPO29】
図2:二つの語彙知識による流暢さに対する説明率の比較
(3)研究の波及効果や社会的影響
第二言語の語彙学習に関して、単語と意味の単純な繋がりを超えて語彙知識を最終的には自動化していくことが、現実の言語使用場面で使える語彙知識を得るために重要であることが示唆されました。今回焦点を当てた発話の流暢さは、円滑なコミュニケーションを実現する上で最も大事な要素の一つであり、また、言語の習熟度そのものを表す指標でもあります。流暢さの中でも特に「節内で発生する沈黙」は円滑なコミュニケーションを阻害する要因になり得ることを踏まえると、外国語の学習またその指導にあたっては積極的に語彙知識の自動化に向けて学習していくことが望まれます。加えて、自動化語彙知識は「音声で英文を聞いた時に素早く認識できる語彙知識」であることから、本研究によって音声で語彙を学ぶ重要性が再認識されたと言えます。日本の教育現場では語彙を覚える時に文字情報から学ぶことが多い現状があり、発音習得やリスニング能力の観点からも音声で語彙を覚えることの恩恵は多岐にわたります。
(4)課題、今後の展望
本研究では、自動化語彙知識との比較として従来型の語彙知識を測定しましたが、単語の意味を選択肢から選ぶ形式のみを使用しました。従来型の測定方法は様々あるため、今後の研究では単語自体を思い出す発信型の語彙知識なども含めて広く測定し、比較する必要があると言えます。また、発話の流暢さにとって重要であるとされている文法の処理速度は今回測定しておらず、流暢さに対する言語知識の豊富さや言語処理の速さの重要性を総合的に評価するためには、自動化語彙知識と同時にこれらの測定を行い、分析に含める必要があるでしょう。
(5)研究者のコメント
本研究での「自動化語彙知識」というコンセプトは、第二言語の語彙習得研究で長らく通例となってきた多次元モデルを一歩拡張する可能性を秘めています。リスニング能力との関連を調査するプロジェクトとして始まったこの一連の研究によって、今回スピーキング能力に対してもその重要性を示唆する結果が得られました。語彙知識と言語使用の理論的なつながりが徐々に明らかになってきており、今後は「どうすれば語彙知識が自動化するのか」という教育的観点からも研究を進めていきたいと考えております。
(6)用語解説
※1 節内で発生する沈黙の数
英語の文は「節」という単位に分解することができます。英語母語話者は節の途中で止まることは少なく、節の境界で止まることが多いとされています(I think…it might be true that…)。一方、英語の学習者は節の途中で止まることが多いことがわかっています(I…think…it might be…true…that…)。このことから、節の境界で発生する沈黙は「次に話す内容を考える」ためのものであり、節の途中で発生する沈黙は学習者の「言語知識の不足・処理速度の遅さ」を表していると言われています。
※2多次元モデル
Paul Nation氏によって提唱されたこのモデルでは、語彙知識には全部で9つの側面があるとしています。
語彙の形式について、(1.1) どのような音なのか、(1.2) どのような見た目なのか、(1.3) どのようなパーツで構成されているのか
語彙の意味について、(2.1) どのような意味を表すのか、(2.2) どのようなコンセプトを持つのか、(2.3) 他の語彙とどのような意味的つながりを持つのか
語彙の使用について、(3.1) どのような品詞で文法的機能を持つのか、(3.2) どのような語彙と一緒に使われるのか、(3.3) どのような文脈で使うのが適切なのか
※3 発話生成
Levelt (1989)によれば、人間が発話する時には頭の中で主に3つの処理を経ると言われています。
概念化:言語に関係なく、いわゆる「言いたいこと」が形作られる段階
符号化:概念化で作られた「言いたいこと」に対して、語彙・文法・音韻情報を参照して言語を割り当てる段階
調音化:喉・口・鼻などの調音器官を通して音として発する段階
これらの処理段階はモニタリングという機能によって、同時的に注意が払われます。
※4 書き起こしコーパス
リスニング音源を文字に書き起こし、データベース化したもの。
(7)参考文献
[1] Saito, K., Uchihara, T., Takizawa, K., & Suzukida, Y. (2023). Individual differences in L2 listening proficiency revisited: Roles of form, meaning, and use aspects of phonological vocabulary knowledge. Studies in Second Language Acquisition, 47(1), 26-52. https://doi.org/10.1017/S027226312300044X
[2] Uchihara, T., Saito, K., Kurokawa, S., Takizawa, K., & Suzukida, Y. (2024). Declarative and automatized phonological vocabulary knowledge: Recognition, recall, lexicosemantic judgement, and listening-focused employability of L2 words. Language Learning, 75(2), 458-492. https://doi.org/10.1111/lang.12668
[3] Matsuura, R., Suzuki, S., Takizawa, K., Saeki, M., & Matsuyama, Y. (2025). Gauging the validity of machine learning-based temporal feature annotation to measure fluency in speech automatically. Research Methods in Applied Linguistics, 4(1), 100177. http://doi.org/10.1016/j.rmal.2024.100177
(8)論文情報
雑誌名:Applied Linguistics
論文名:Automatized phonological vocabulary knowledge as L2 cognitive fluency: Testing the declarative–automatized integrative model in L2 speech production
執筆者名(所属機関名):*瀧澤嵩太朗1, 斉藤一弥2,3, 鈴木田優衣2,3, 黒川皐月3, 内原卓海3
1: 早稲田大学大学院教育学研究科 2: ロンドン大学教育研究所 3: 東北大学大学院国際文化研究科
掲載日時(現地時間):2025年7月7日
掲載URL:https://doi.org/10.1093/applin/amaf042
DOI:10.1093/applin/amaf042