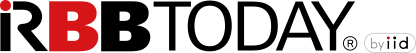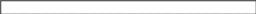
1.概要
泡(注1)は洗浄剤や食品、化粧品、消火剤、資源回収など、日常や産業で幅広く利用されています。これまで泡の吸収能力(もしくは、液体をどれだけ保持できるか)は、「浸透圧(注2)」で決まるとされてきました。しかし、実際の泡は理論よりもはるかに小さい状態で水を流し出すことが知られており、その理由は謎とされていました。
東京都立大学大学院理学研究科 物理学専攻の金田蒼依(当時:大学院生)、栗田玲教授の研究グループは、泡の吸収限界について詳細に測定し、従来理論の30分の1という非常に小さな「実効浸透圧」が実際の吸収限界を支配していることを発見しました。この限界は、液体の流動と泡内部の気泡の運動が結合しており、「泡の力学応答」によって決まることが明らかになりました。
泡のような「ソフトジャミング系(注3)」では、溶媒の動きを無視されることがほとんどですが、この発見により溶媒と溶質の動力学的な結合が重要であることを示しています。今後の洗浄方針や医療材料設計にも応用だけでなく、ソフトジャミング系の学術的な進展が期待されます。
■本研究成果は、5月8日付けでElsevierが発行する英文誌Journal of Colloid and Interface Science に発表されました。本研究の一部は、学術振興会科学研究費補助金(基盤B No. 20H01874)の支援を受けて行われました。
2.ポイント
1.泡の吸収限界は、従来考えられていた「浸透圧」ではなく、泡の力学特性(降伏応力(注4))によって決まることを発見しました。
2.実効浸透圧は最大でも約70 Paとなり、理論上の浸透圧(2000 Pa)に対し、30分の1以下であることが判明しました。
3.吸収限界は、泡の表面張力と気泡サイズの比に比例し、界面活性剤の種類や崩壊のしやすさに依存しない。
4.この力学的応答は、血流やエマルションなど他の「ソフトジャミング系」に共通する性質であり、基礎物理から応用分野までの発展が期待されます。
3.研究の背景
泡は気泡が液体中に高密度に詰まった状態であり、吸収性・断熱性・保持性といった特性を持つため、多くの分野で利用されています。中でも「液体をどれだけ保持できるか(吸収限界)」は洗浄剤や環境技術にとって極めて重要な指標です。
泡の内部では、気泡が押し潰されている状態になっています。この押し合いのため、気泡と液体の表面積が増加し、表面エネルギーを損失している状態です。この表面エネルギーの損失が「浸透圧」の起源であり、理論的には気泡サイズや液体分率、表面張力によって計算され、この浸透圧分だけ液体を吸収することが可能とされています。理論上の浸透圧(2000 Pa)となり、1メートル以上の高さの泡でも水が排水されないことになりますが、実際には数センチメートルの高さになると吸収限界を超えてしまい、泡から水が排水されます。長年、この理論と現実との間にあるギャップの理由は不明のままでした。
4.研究の詳細
本研究グループは界面活性剤溶液から市販の泡ポンプによって泡を生成し、2枚のアクリル板に挟んで鉛直に立てて、排水されるかどうかを観察しました(図1)。泡の高さ【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O4-nf6p0cyR】 が泡内部の溶液の重力による圧力を決めるパラメータとなっており、【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O4-nf6p0cyR】 が大きいと泡の浸透圧を上回り排水します。逆に【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O4-nf6p0cyR】 が小さいときは排水されないと予想されます。
TTAB,SDS,市販の界面活性剤を用いて、気泡の平均サイズや液体分率【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O5-Uc5udzS8】 、粘性、泡の高さ【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O4-nf6p0cyR】 を変えて実験を行い、排水されるかどうかを観察した結果、この排水条件が【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O6-u998Bk2Y】 (【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O7-nWoaPzaw】 は定数)で決まることがわかりました。図2は縦軸【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O8-xjX234lz】 ,横軸【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O5-Uc5udzS8】 ですべての実験条件での観察結果をまとめたものです。界面活性剤の種類や気泡の平均サイズ、粘性によらず、排水条件が【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O6-u998Bk2Y】 で普遍的に決まっていることがわかりました。
重力と浸透圧のつりあいから、実効的な浸透圧【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O9-05K8Ml8X】 は密度ρを用いて以下の式から求めることができます。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O10-fg7YISQe】 (1)
この式から実効的な浸透圧を求めると最大でも約70 Paとなり、理論上の浸透圧(2000 Pa)に対して30分の1以下であることが判明しました。また、【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O11-A9NOQzcU】 (【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O12-t2VOZ1JP】 は表面張力)という関係式が得られることがわかりました。実効的な浸透圧は吸収能力と同等ですので、気泡が小さく、表面張力の大きい方が吸収能力も大きいことを意味しています。
このような理論と実効的な浸透圧との差を解明するため、内部構造の変化を観察しました。図3は排水されるときと排水されない時の内部構造の変化を示したものです。排水されない時は気泡がほとんど動いておらず、排水される時は気泡が再配置していることがわかります。この再配置は、泡にかかる応力が「降伏応力(yield stress)」を超えるときに起こります。実験により得られた実効的浸透圧が【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O13-7q97Egji】 に比例することは、「降伏応力」のスケーリングと一致し、実際に泡の降伏応力はおよそ50 Paであることが知られており、今回の測定結果(最大70 Pa)と整合します。つまり、液体が排出されるかどうかは、泡内部で気泡の再配置が起こるかどうかで決まり、その発生条件は降伏応力によって支配されているという新しい物理的理解が得られました。
この研究成果は泡の洗浄能力評価にも用いることができます。式(1)は、表面張力や気泡サイズの精密測定、液体分率を調べる必要はなく、排水の有無を調べるだけで、実効的な浸透圧を求められることを意味しています。排水する時はすぐに排水されるため、一回の測定は5分程度で行えます。アクリル板に挟んで垂直に立てるだけの簡単な測定法で短時間に精密に測定できる点は、今後、泡の評価方法の一つとして、界面活性剤の選定や配合設計における新たな指標となる可能性が期待されます。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O14-eJ9R2M2k】【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O15-DInyo997】
図 1 実験装置の概要図。泡を2枚のアクリル板で挟んで垂直立て、排水されるかどうかを観察する。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O16-7G7qB70v】
図 2 さまざまな実験条件における排水の有無の状態図【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O6-u998Bk2Y】で分離されることがわかった。【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O17-f568Rup7】 【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202505148803-O18-3gaHXre1】
図3 (a)-(c)の非排水条件と(d)-(f)の排水条件におけるフォーム基部の内部構造変化。(a)と(b)は、t = 14.6秒とt = 20.0秒における気泡の位置を示している。(c)は(a)と(b)から気泡界面を抽出して重ね合わせたものである。非排水条件下で気泡が静止している。(d)と(e)は、排水条件でのt = 5.8秒とt = 11.4秒の気泡位置を示している。(f)は(d)と(e)から気泡界面を抽出して重ね合わせたものである。(f)は(d)と(e)から気泡界面を抽出して重ね合わせたもので、気泡が大きく再配列していることがわかる。矢印は再配置した気泡の変位を示す。
5.研究の意義と波及効果
この研究成果は、泡の「吸収量」の短時間評価を可能にする手法の基盤となるとともに、泡製品の設計における基準指標の提供が期待されます。また、これまで「静的」で考えられてきた泡の力学的モデルを、動的かつ非平衡的なモデルに見直す必要性を示しています。
本成果は、泡の物理にとどまらず、血液や組織など他のソフトマター系の流動や吸収挙動にも応用可能な普遍性を持つと考えられます。
【用語解説】
専門用語の解説
(注1)泡:少量の液体に気泡がぎゅうぎゅうに詰まっている状態のこと。
(注2)(泡の)浸透圧:泡は液体と接触した時、内部に液体を吸い込む。この負の圧力のこと。油であってもこの浸透圧によって吸い込まれる。
(注3)ソフトジャミング系:柔らかい粒子が押しつぶされながら詰まっている系のこと。
(注4)降伏応力: 泡のように詰まっている系は大きな力を加えると変形するが、小さな力では変形しない。この変形するかどうかの境界を決める応力のこと。
【関連する特許(出願中)】
栗田玲,金田蒼依
出願番号:特願2023-149078
出願日:2023年9月14日
発明の名称:洗浄力の評価装置、洗浄力の評価方法
【発表論文】
“Absorptive limits of foams governed by kinematic coupling between solution and bubbles”
Aoi Kaneda and Rei Kurita, Journal of Colloid and Interface Science(2025)
DOI: 10.1016/j.jcis.2025.137746