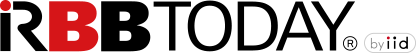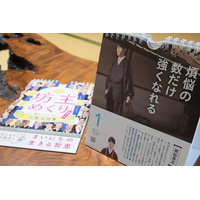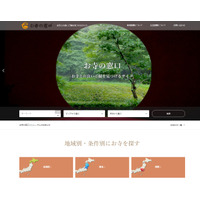日本一ありがたいASMR
このコラムで比叡山の「VRお寺参拝」を紹介したことがある(第13回「仏教×VR」の2つの可能性)が、また新しい形のバーチャル参拝が誕生した。全9本の動画から、気分に応じてお寺の“音”を処方してもらう「知恩院サウンドセラピー」である。浄土宗総本山の知恩院が今年1月に公開したもので、たとえば、「無心になりたい」ときに処方されるのは、ただ念仏を唱えながら木魚を打つお坊さんの映像。あるいは、「ひと息つきたい」ときの処方は、お坊さんがお堂の扉を開ける映像。日本に古くから伝わる風景を眺め、そこに響く音に耳を澄ますことで、せわしない日常からひとときでも解放されてほしいと願って作られている。

気が利いているのは、上の映像も含めいくつかは、バイノーラルマイク(音を立体的にとらえるステレオマイク)を用いて録音されていることだ。つまり、音フェチが好むASMR(視覚や聴覚の刺激によってもたらされる心地よい感覚)動画になっていて、イヤフォンやヘッドフォンで聴けば、お寺の音や読経の声がリアルに耳元で響き、懐かしい世界が広がる。私の周囲にも聴かせてみたら、若い世代には特に評判がよく、ITによるバーチャル参拝は一段と身近になったと感じ入っている。
この知恩院サウンドセラピーは、9年に及んだ国宝御影堂の半解体修理工事がいよいよ終わり、落慶を迎えるタイミングで知恩院に関心を向けてもらうためのものだった。当初の目的とは異なるが、コロナ禍に見舞われステイホームが要請されている状況では、家で静かにお寺を感じてもらうツールとして生きることになった。

コロナ禍のなかのお寺
いまのところお寺に「休業要請」が出されているわけではないが、コロナ禍のために大きな打撃を受けているのは、企業だけではなくお寺もやはり同じである。観光収入を主たる収入としているお寺のほうが経済的影響は深刻だろうが、信仰の拠点として存在しているお寺も、身動きが取れず苦しんでいる。信者が堂内に集まれば「三密」になってしまうので、法要などの行事が行いにくいからである。この観点においてもっとも顕著な影響を受けたのが、コロナ禍と御影堂落慶が重なった知恩院だろうと思う。
本来の予定では、この4月13日から3日間にわたって落慶法要を迎え、境内は大いに賑わうはずだった。その後も4月18日から25日までは「御忌大会」という宗祖を供養する大法要があり、その初日の「ミッドナイト念仏 in 御忌」には千数百人が国宝三門にお参りし、夜通し念仏するはずだった。しかしながら、感染リスクを避けるため、このすべてが中止あるいは徹底的な規模縮小を余儀なくされた。落慶した本堂にご本尊を迎える法要は関係者のみで執り行われた。法要の風景は、代わりにYouTubeの浄土宗公式チャンネルで配信された。ミッドナイト念仏が行われるはずだった夜は、中の人たちが朝までツイッター上で念仏を続けた。サウンドセラピーのASMR動画を含め、バーチャルでの参拝者はにぎわったが、御忌大会期間中の境内はひっそりとしていた。

オンラインにふさわしい仏事
バーチャル参拝の試みは他のお寺でも急速に普及している。法要に参拝者を招かず配信のみで実施したり、世の中の安寧を願って宗派を超えて読経リレーを実施したり、法話のライブ配信を行ったりと切り口も様々だ。オンラインコンテンツが増えたことに、「有難い」と一定の評価はなされているようだが、一方で「オンライン疲れ」もささやかれる。
私に対しても、オンラインで読経を配信してほしいという声も寄せられたが、どうも気乗りがしなくて実施していない。いつもリアルな空間でつとめている法要や法事をそのままオンラインで配信したところで、現場の空気感がまるで失われて退屈だと思うからである。オンラインでやるなら、オンラインのロジックでやるべきである。その意味において、松崎智海さんの「オンライン花祭り」はよくできていた。
本日はお釈迦様の誕生を祝う花まつりの日ですが、こんな状況なので参加できない方も多くおられると思います。そこでこのツイートのリツイート数だけ住職が代わりにお釈迦様に甘茶をかけます。リツイートのカウントは4/8の正午までとします。 pic.twitter.com/LCP2MisREM
— 松崎智海(非売品僧侶)@浄土真宗本願寺派♪永明寺住職 (@matsuzakichikai) April 7, 2020
4月8日にお釈迦さまが生まれたとき、甘露の雨が降ったという言い伝えにちなみ、お釈迦さまの誕生を祝う「花祭り」では参拝者が釈迦像に甘茶をかける。しかしながら、今年は花祭りにお参りいただけないため、リツイートされた数だけ住職が代わりに甘茶をかける、と松崎さんはツイートした。そうすると、これが大いにバズり、リツイートは期限の正午までに32,551回を数えた。松崎さんはこの“緊急事態”を楽しく受け止め、甘茶をかける様子をライブ配信し、翌日までかかって32,551回をやり遂げた。松崎さんのこの企画ぐらい「オンラインらしさ」があってこそ、オンラインでやる意味がある、と私は受け止めている。
コロナが打ち破ったお寺の旧習
いずれにしても、コロナ禍でお寺の本堂が使えないために、多くのお坊さんがオンラインでの布教を導入することになったのは、今後のお寺の姿を考えるうえで大きな前進である。
コロナ禍のいまは、感染対策の観点から「オンライン葬儀」「オンライン法事」が真剣に検討されている。しかし、思い返せば、私自身がこれまでつとめたお葬式でも、ご遺族が海外勤務や海外旅行中で帰国が間に合わず、参列を断念されたケースがある。海外に中継することもできたはずだが、コロナ以前は、「オンライン葬儀」はどこか非常識なにおいがあり、私からもご遺族からも言い出しにくかった。
オンラインの葬儀や法事が普及すると、親族が集まらなくなると危惧する人もあるかもしれないが、これはもうグローバル化した時代には受け入れていくしかない。ただ、その際、単にオンラインに載せるだけなら、弔意がどうしても伝わりにくくなる。リモートだと焼香もできないから、代わる仕組みも必要だろう。本当に供養の心のこもった葬儀や法事とはなにか。供養の形をゼロベースで考えるべき時期がいま訪れているといえるだろう。

【著者】池口 龍法
1980年兵庫県生まれ。兵庫教区伊丹組西明寺に生まれ育ち、京都大学、同大学院ではインドおよびチベットの仏教学を研究。大学院中退後、2005年4月より知恩院に奉職し、現在は編集主幹をつとめる。2009年8月に超宗派の若手僧侶を中心に「フリースタイルな僧侶たち」を発足させて代表に就任し、フリーマガジンの発行など仏教と出合う縁の創出に取り組む(~2015年3月)。2014年6月より京都教区大宮組龍岸寺住職。著書に『お寺に行こう! 坊主が選んだ「寺」の処方箋』(講談社)、寄稿には京都新聞への連載(全50回)、キリスト新聞への連載(2017年7月~)など。
■龍岸寺ホームページ http://ryuganji.jp
■Twitter https://twitter.com/senrenja